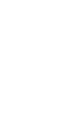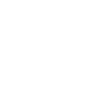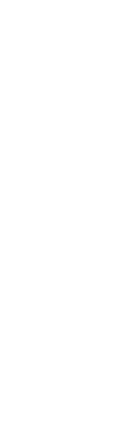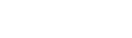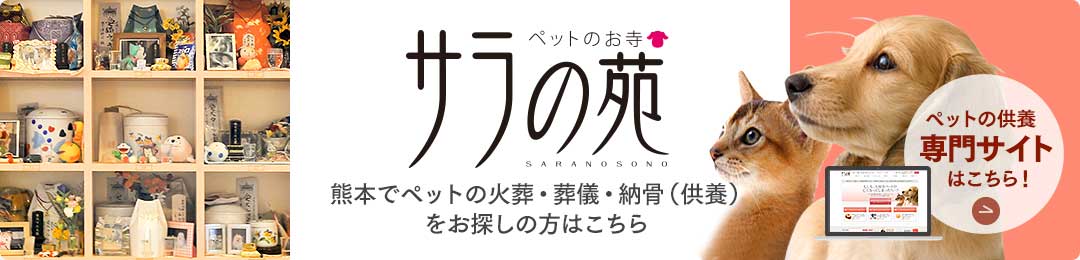“ご供養”
盂蘭盆会万燈供養

万燈供養とは自身の先祖のみならず、縁の有る無いに関わらず、その無限なる命に対し報恩の祈りを込め、あわせて、暗闇を照らす智慧の光である燈明を仏さまにお供えし、その功徳をすべての命に廻らす古くより伝わる仏教法要です。
- 開催日8月11日(祝・月)第1部/17:30〜 第2部/19:30〜
- 場所公園墓地菩提樹苑内 慧日堂(納骨堂)google map
- 供養料1霊 3千円
- 献灯料1灯 千円
- 献花料1基 3千円
過去の盂蘭盆会万燈供養の様子はこちら
春・秋のお彼岸会法要

お彼岸とは、我々のいる迷いの世界(此岸)に対し、仏様の世界・心理の世界・本当の世界を差し、極楽浄土とも呼ばれます。一年中で昼夜の長さが同じく「暑からず寒からず」のこの7日間を「お浄土」と見立ててお寺へ参拝、お墓参りをすることでご先祖様の御霊を弔います。同時に、自らの日頃の行いを反省し、仏教の精進努力(自分の心を磨く)の機会とします。
また、二十数人が円座になり、直径3メートルほどの巨大なお念珠を、念仏を唱えながら回す「百万遍の念珠の会」も同時開催。家族で参加し、ご先祖様をみなで敬いませんか。
法要が終わった後は、坊守手作りのお斉(おとき)= お昼御飯のお接待もご準備しております。さらに、ご供養をしたという証となる「廻向の証」を授与します。
- 開催日例年 春分の日(3月20日前後)、秋分の日(9月21日前後)
- 場所本蔵院 本堂
- ご廻向料1霊5千円
- 献灯料1灯5百円
水子供養

流産、死産、中絶など、やむを得ない事情によってこの世に生まれることなく亡くなった赤ちゃんがいます。深い悲しみを、誰にも話せず抱え込んでいる女性もいることでしょう。本蔵院にお越しいただき、いろいろな思いをお話しください。赤ちゃんの霊を供養し、水子地蔵様に導きお守りいただきます。
まずお電話でご予約下さい。なお、プライベートは守られますのでご安心ください。
- ご供養料5千円~
※完全予約制となっております。ご来院のまえにお電話かメールフォームにてご希望する時間などをお知らせください。
永代供養
お葬式

お葬式とは、亡くなられた故人を出家得度させ、仏の世界極楽浄土へと導く大変大切な儀式であります。
最近では、お葬式をしないですぐ火葬をする「直葬」といったメディアの造語が広く知られるようになりましたが、当院は「死」という事こそ、我が命を考える最大の機縁であると考え、施主様の心に寄り添ったお葬儀を勤めております。
- お葬式までの流れについて
-
お葬式までの流れ(例)
お亡くなりになったら…
- 葬儀社に連絡
- 落ち着かれてから、寺院への一報を
- 枕経(亡くなってすぐのお経)
- 戒名を準備するため、故人のお人柄を伺います
- 通夜法要
- ご葬儀
ペットの供養
仏壇・位牌・墓地の入魂・抜魂

開眼供養(お魂入れ)
位牌、お墓などは、そのままではただの木や石。仏の魂を入れ、仏の眼を開く事が重要です。仏壇や位牌、墓地を新しくしたときには、僧侶の読経で供養し、魂を入れることで、仏壇や位牌、墓地に初めて仏が宿ります。
- ご供養料1万円~
撥遣(はっけん)供養(お魂抜き)
これまで供養してきた仏壇、位牌、墓地などを修復や処分のほか、移転する際には、仏の魂を抜き、一度お浄土にお返しします。修復や移転の場合は、修復や移転が完了した後にあらためて新しいものに魂を入れる開眼供養が必要です。
- ご供養料1万円~
※開眼供養、撥遣供養を同日に行うことも可能です。
法事について

仏教では、亡くなられた後に回忌に沿って法事を営みます。亡くなられた方のご実家のほか、お寺で執り行うこともできます。一般的に、亡くなった翌年の命日に行う一周忌、亡くなった年を入れて3年目が三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、三十三回忌、五十回忌と続きます。
本蔵院では、お食事の準備なども含め、法事のすべてをお手伝いできます。ご希望の方はご相談ください。
- ご供養料3万円~
- 法事の打ち合わせ
-
法事の打ち合わせ
- 日程を決めます。
命日に近いご家族がお集まりやすい日をお選びください。 - 場所を決めます。
ご自宅の仏壇もしくは本蔵院本堂をお使いいただく事も可能です。 - お食事を決めます。
本蔵院書院をご利用いただけます。人数や料理内容を打ち合わせます。 - 最終的な人数を決めます。
遅くとも一週間前までにはご連絡ください。 - 持参するものの確認
- 位牌(忌明けなら白木位牌)
- 遺影
- 遺骨(納骨する場合)
- 引き出物
- 日程を決めます。